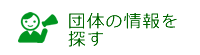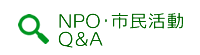山形市で開催されている「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」は東日本大震災をきっかけに生まれたアートのフェスティバルです。開催場所は「文翔館エリア」と、「東北芸術工科大学エリア」に分かれており、今回は「文翔館エリア」を中心に取材に伺いました。

「ビエンナーレ」は「2年に1度」というイタリア語から転じて「2年に1度開かれる美術の展覧会」を指します。東北芸術工科大学が主催するこのビエンナーレは、今年で3回目の開催です。今回のテーマは「山のような」。このテーマには山形らしい「山のような」芸術、アイデアを「山のように」だしながら、という意味が込められています。テーマの通り山形に密接な展示が特徴的な芸術祭です。
メイン会場の文翔館では、山形をモチーフにした作品や伝統工芸を使った作品だけでなく、タッチパネルやプロジェクションマッピングを使った先進的な展示もあります。

文翔館の議場ホールで展示されていたのは、山形市出身の絵本作家、荒井良二さんが監督した「山のヨーナ」です。「山のヨーナ」は、荒井さんが考案していた絵本のタイトルだったもので、山で小さなお店を営みながら暮らしているヨーナが、街や海などから来たお客さんのお話しと交換に小さな人形を手渡しながら、物々交換で人々と交流していく物語です。絵本のストーリーにちなみ、ヨーナのお店をモチーフにした屋台では、来場者が持ってきた手のひらに乗るような小さなものと交換でヨーナが作る人形をもらうことができます。
文翔館を使った展示は、それぞれの作品が文翔館の雰囲気と融合し、普段感じることのない非日常感が醸し出されているように感じました。
七日町では、老舗の店舗や蔵を利用した会場が中心になっています。雑居ビルをリノベーションした「とんがりビル」や、かつて書店として運営していた「郁文堂書店TUZURU」での展示、元は洋傘店だった店舗を利用したカフェ「BOTAcoffee」、明治時代の石材で復元された蔵を利用した「gura」、長門屋が所有する「ひなた蔵、塗蔵」での映像の上映など、どの会場でも独自の内装や、独特な香りのような建物の魅力が生かされています。

「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」は芸術作品の発表の場であると共に、芸術を通じた地域での交流の場でもあります。アートの非日常にも見える風景の中で山形の伝統的な工芸や食材を利用することで、「古き善き」を取り入れながら新しい山形を発見できる、山形にとても馴染んだ山形ならではのまちづくりの取り組みでもあると感じました。
主催:東北芸術工科大学
お問い合わせ先
東北芸術工科大学 山形ビエンナーレ事務局
TEL: 023-627-2091
E-mail: biennale@aga.tuad.ac.jp