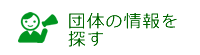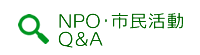令和3年10月30日(土)に、「SDGs(持続可能な開発目標)」と、社会的な課題について関心を寄せる方々に向けて「SDGsミーティング」を開催しました。
この「SDGsミーティング」は昨年の10月より定期的に開催しており、今回で7回目となります。
今年度は、SDGsに関係する社会的な課題をテーマに、毎回3名の方をパネリストに招き、日頃の取り組みについてお聞きして理解を深めるパネルトーク形式で行っています。

今回は「ジェンダーの観点から誰一人取り残さない社会を考える」をテーマに、山形県男女共同参画センター館長の伊藤眞知子氏、産婦人科医の金子尚仁氏、NPO法人山形県青年海外協力協会の岡部幸子氏を招いて、当センター所長の有川がコーディネーターを務め、ジェンダー平等が達成されていないと感じることや、様々な課題を解決して行くためには何が必要でどんな取り組みが求められるのか、そして、これから取り組むべきことなどについて理解を深めました。
当初、パネリストの方々はZoomでの登壇の予定でしたが、その後当センターに来館いただくことになり、会議室Bをパネルトークの発信場所として用意しました。そして、会場で受講された方々には、センター内の別の場所で、Zoom上の画面を投影して視聴いただきました。また、オンラインで参加されたとある団体の方々は、別の会場を借りての集合研修でパネルトークをご覧になっていた様でした。
ジェンダーについての専門家である伊藤氏、医学的な観点で話題をして頂いた金子氏、外国籍や日本に帰化した方々の相談員としての経験をお持ちの岡部氏による意見交換には受講者も刺激を受けた様です。多くの感想が寄せられましたので、下記にてご紹介します。
・「当たり前を疑ってみる」この言葉にドキッとした。コミュニティの常識に埋もれている自分を客観視しなければと反省した。
・ジェンダー教育を受けていない私たち世代には、理論として理解できても、「女性らしく」「男性らしく」の躾が身についてしまっている様な気がする。
・自分が普通と思って発する言動が差別となってはいないだろうか。
・国が制度や仕組みとして正面からジェンダー問題に取り組まず、民間の活動にのみ頼ってきた結果が今の日本なのではないだろうか。やんわりな変化と地道な民間活動だけではなく、政治を動かす活動と両軸で考えたい。
・ジェンダーの不平等については過疎化が進む地域こそ女性等の言動は大きく制約を受けている様に感じた。こうした地域環境の中では有能な女性は潰されてしまって、結果的に都市部に流出してしまっているのではないだろうか。
・子どもたちが抱える問題には、時代に合わない教育システムの一つとしてジェンダーバイアスも関連していることに気づくことができた。若者(特に男性)のひきこもりもジェンダーバイアスが通っている社会背景が要因として大きい様に感じた。
・外国から嫁いできたマイノリティの人々の苦しさ、生きづらさを知る事が出来た。もし、近くにそのような方々がいれば進んで声掛けしたいと思った。
次回の「SDGsミーティング」は現在企画を検討中です。詳細が決まりましたらウェブサイト等でお知らせします。
文責:「SDGsミーティング」 担当 黒木伸悟