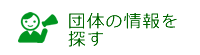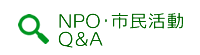11月6日(日)、公益社団法人認知症の人と家族の会が主催する第38回全国研究集会がやまぎんホールにて行われました。
この全国研究集会は、認知症の人の対応に悩む家族や支援する人たちが、交流を通してよりよい支援や介護のあり方を共有し、広く社会に普及するという目的で1985年から始まりました。今年度は山形での開催ということで、認知症の人と家族の会山形県支部の方々が事務局となり、準備や当日運営を担当しました。参加方法は会場参加の他に、オンラインでの参加もあり、合わせて約750名の参加がありました。
会場入り口には山形県内で開催されている「つどい」ののぼり旗が、エントランスには全国各地の「つどい」のポスターが展示されていました。認知症の「つどい」は全国支部で実施されており、どの地域のポスターも写真が多く、参加者の楽しそうな様子が伝わってくるものばかりでした。
 |
 |
全国研究集会は午前の部と午後の部に分かれていて、私が参加した午後の部の様子をご紹介いたします。なお、午前の部では劇作家の渡辺えりさんの特別講演と、福岡県と福島県の認知症の方の体験発表がありました。
午後の部は、鳥取県の「カヌー作りを通して広がった活動」と、山形県の「認知症となった方の生活を支える後見人の役割について」というテーマで体験・実践発表がありました。

鳥取県の米村さんは認知症と診断されてから自分と同じ認知症の方々や地域の包括支援センターの協力で「山陰ど真ん中」という団体を立ち上げたこと、以前から夢だったカナディアンカヌーづくりを通して、多くの人と交流していきたいということをお話されました。私が印象的だったのは、米村さんが最後に「めげずに、嫌な事もあるけど頑張っていこう」と言っていたことでした。若年性認知症と診断されてから、多くの人の協力があり、今は「山陰ど真ん中」の活動を通じて毎日楽しく過ごしているという米村さんのお話を聞くと、元気をもらい前向きに頑張ろうと思いました。
その後に「安心して語ることができる場の役割について考える」というテーマでシンポジウムがありました。シンポジストは、家族の会世話人「つどい」運営者の工藤さん、「つどい」の参加者の土田さん夫婦、福島原発事故に伴う帰還困難者の当事者でもあり支援者の辺見さん、難病カフェin庄内の主催者でもあり難病当事者の梅津さんの4名。

その中でも、妻が認知症と診断されてから「つどい」に参加したという土田さんは、「2021年8月、認知症の人と家族の会の集まりに妻と一緒に参加したことで、自分と同じ境遇の人たちや、家族の会の皆さんの支援を受けることができた。皆さんが温かく迎えてくれたことで、社会とのつながりが生まれ、妻も得意なピアノを披露し、毎日を楽しく過ごしている」という、認知症となった方が安心して相談できる場として「つどい」があったことを、自身の経験をもとにお話しいただきました。

最後に福島県立医科大学・会津医療センターの川勝教授がシンポジスト4名のお話を総括して、「認知症などの症状の方の治療で重要なことは、安心して自分の考えを話せる場があるかです」、とまとめアルツハイマー型認知症の治療薬が開発されていることや、難病の患者に対してコミュニケーションを取りながら治療方針を決めていくことなど、難病の治療の現状についても説明していました。

今回は午後からの参加となりましたが、この全国研究集会で認知症となった方々の体験や、支援団体の皆さんの活動を聞き、より身近に認知症についての理解を深めることができました。また、認知症に限らず、自分の想いを話すことができる「つどい」のような場の必要性についても改めて考えさせられました。当センターにも、認知症の人と家族の会の他にも、様々な難病を抱える人、それを支援する方々の団体が登録しており、定期的にお話会や相談会を行っています。今後もそのような活動の様子を発信していきたいと思います。
- お問い合わせ先
公益社団法人 認知症の人と家族の会 山形県支部
TEL:023-687-0387