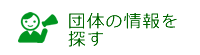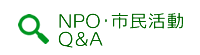山形市市民活動支援センター主催
「性の多様性~女と男とLGBTと~」を開催しました
令和5年6月11日(日)に、性の多様性の理解や性による無意識の偏見の排除を目的とした講座を開催しました。
講師は天童市民病院産婦人科医長の金子尚仁さんです。当日は29名の方々に参加いただきました。今回は山形市内だけではなく、寒河江市、天童市、東根市、河北町、村山市など広い地域からの参加が見られました。参加いただいた方の年齢も学生から70歳代までと幅広いのが特徴的でした。

講座の内容は、まず性の多様性の理解から始まりました。性には生物学的な側面と社会的・文化的な面と法律的な側面があること。そしてその性の目的は何かということを学びました。次にジェンダーと言われる男らしさや女らしさは国や文化、時代によって変わること、そして男性像や女性像は社会の中で形作られてきたある種のイメージであること、普遍的な男らしさや女らしさは存在しないことなどを共有しました。
私達の性別は複数の要素の組み合わせによって様々なセクシャリティ(性のあり方)が形作られます。この組み合わせは多様で、性はグラデーションとも言われること、性的マイノリティ(性的少数者)の方をLGBTQ+と表現すること、そしてそれぞれどんな意味なのか、どんな人達を指すのか、性自認や性指向、性表現について学びました。
次に性別変更について、日本の性別変更手術の現状や性別変更の要件、性別変更のための手術の話を聞きました。講師から紹介いただいた性別変更の裁判例は、具体的でとても引き込まれるものがありました。諸外国の性別変更の要件と日本との違いもわかりやすく解説いただきました。
自然界ではオス・メスという性は曖昧なこと、ヒトでも生物学的な性や社会的・文化的性は曖昧であること、日本のLGBTQ+の頻度は約8%であること、典型的な男女に当てはまらない存在にどう対処したらいいかわからず、困惑するため、男女に二分することが多いのではないかと話されました。
最後に講師からは、多様性を認める社会では差異を巡る差別構造や不平等があってはならないこと、社会における無意識の偏見から脱却することも必要であること、そしてそのためには、日常生活の隠れたカリキュラムをなくすこと、不要な男女の区別をなくすこと、性別役割分担を考え直すこと、ジェンダーは女性だけではなく誰もが考えるべき問題ではないかとのメッセージを頂きました。
会場の参加者は皆熱心に講師の話に耳を傾けていました。たくさんの質問も寄せられて、盛り沢山な内容となりました。
文責:「性の多様性~女と男とLGBTと~」 担当 有川富二子