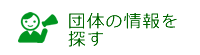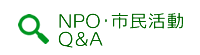解散をする場合は以下の流れになります。
・ 社員総会において解散を決議する。
・ 法務局において解散及び精算人の登記を行う。登記後、所轄庁に解散届出書、登記事項証明書を提出する。
・ 山形地方裁判所の監督により、清算業務を行う。
・ 法務局において清算結了した旨の登記を行う。登記後、所轄庁に清算結了届出書、登記事項証明書を提出する。
また、特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 法第43条の規定による設立の認証の取消し
このうち、3の「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由とする解散については、所轄庁の認定がなければ効力を生じません。(同条第2項、3項)
なお、法人が解散した場合、その法人は清算法人となり、清算の目的の範囲内において、清算の結了まで存続するものとみなされます。(法第31条の4)
清算事務の執行にあたる者を清算人と呼び、その主な職務は、次のとおりです。(法第31条第4項、法第31条の9、法第31条の10、法第31条12、民法第78条)
- 解散事由が1、2、4、6の場合には、所轄庁へその旨の届出
- 現務の結了 (現に継続中の事務を完了させること)
- 債権の取立及び債務の弁済
- 残余財産の引渡し
- 債権の申出の公告と催告
- 公告と催告により判明した債務の分配
清算人は、破産での解散を除き、原則として理事が就任します。ただし、定款又は総会の決議で別に定めることも可能です。(法第31条の5)
また、残余財産の帰属先は、合併及び破産の場合を除き、法第32条で次のとおり決められます。
- (民法第83条に基づく)所轄庁に対する清算結了の届出の時に、定款で定めた者に帰属します。(法第11条第3項) なお、その場合、次の1から6のうちから選定すべきことが義務づけられています。
1.特定非営利活動法人
2.国又は地方公共団体
3.公益社団法人、公益財団法人
4.私立学校法第3条に規定する学校法人
5.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
6.更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
- 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
- 1、2の方法により処分されない財産は、国庫に帰属します。