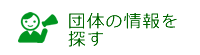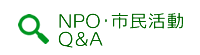第2回日韓国際バイカモサミットが山形で開催されました。
バイカモをテーマに地域環境の再生、民間での国際交流などについて考えようという「日韓国際バイカモサミット」が平成20年10月3日・4日の両日、山形市の遊学館などを会場として開かれました。
バイカモを通した交流のサミットは今回で2回目。第1回目のサミットは静岡県三島市で開催されました。
第2回目はバイカモの生息地である、「山形五堰」を主軸として様々なプログラムが展開されていました。


今回のサミットは五堰の生息地の調査、堰の清掃活動などを行なってきた地元住民でつくる「山形五堰の流れを考える会」や「グランドワーク山形」のメンバーなどが中心となり「日韓国際バイカモサミット実行委員会」が作られ、サミットの準備から開催までを行ないました。

「バイカモ」や「山形五堰」は山形市民にとってなじみが深いと思いますが、ここでちょっとご説明します。
バイカモとは、キンポウゲ科の水生多年草で、山形では6月~7月ごろ、白い5弁の小花を水上や水中に咲かせます。梅に似た花を咲かせるので、梅の花の藻と書きバイカモといわれています。水流に揺れながら咲くその花の可憐さは清涼感にあふれ、見る者を魅了しています。

疎水百選にも選ばれ、農業用水などに利用されています。昔から水車利用や養鯉などの産業のための水、野菜やなべ・釜などを洗う生活に密着した水として、利用されてきました。
このサミットのコンセプトは『「堰」の流れは人の心をつなぎます』
プログラムはとてもユニークで「つたえる・山形五堰研究発表会」「かたらう・日韓食の交流会」「かんがえる・日韓バイカモシンポジウム」「ねぎらう・山形芋煮会」と構成されていました。
サミットのプログラムの一部をご紹介します。
「つたえる・山形五堰研究発表会」
山形市を流れる「山形五堰」の役割や、そこに育つバイカモの生態、山形五堰の水の流れをエネルギーとした研究、堰の流れを利用した新しい町並みの提案など、高校生や専門学校の学生も参加しての発表会でした。
世代や分野をこえて、「バイカモ」と「山形五堰」について新しい活動が生まれる可能性を感じさせる発表会でした。

バイカモを含む五堰の動植物についての調査発表。

五堰の水を活用した水車製作の提言

山形五堰を生かした地域デザインの提案
「かたらう・日韓食の交流会」
山形の良い食材を使った日本と韓国の料理を堪能しました。
会場ではウェルカムドリンクならぬ、五堰の水を使って育てたもち米を使ったウェルカム餅が振舞われました。会場はたくさんのお客様、山形五堰、バイカモの話題でおおいに盛り上がりました。


「かんがえる・日韓バイカモシンポジウム」
静岡県三島市、韓国の江華島、山形のそれぞれの活動について事例発表し、さらに活動を広げるための議論がなされました。韓国からのソウル女子大学教授のイ先生や韓国ナショナルトラスト強化バイカモ委員のハン先生の興味深い内容の発表もありました。
各関係団体の代表者が地域再生、民間の国際交流について話し合う、パネルデスカッションも開催。参加者は有意義な時間を過ごしました。
また「日韓国際バイカモネットワーク推進宣言」がなされ、今後この宣言に基づき、それぞれの活動が活発化し、水環境保全がなされていく社会へと向かうことでしょう。

地域環境改善・まちづくり・歴史文化・国際交流などの多様な活動に関心のある一般市民、関係者が参加したサミット。「バイカモ」や「堰」を介して私たちに伝わったメッセージは素晴らしいものになりました。今回のプログラムは、地域課題や環境保全の課題を捉えそれを解決する知恵や、地域の未来の可能性を再認識できる内容でした。
「日韓国際梅花藻サミット実行委員会」の皆様、そして参加した多くの方々お疲れさまでした。