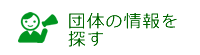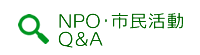「地域力共創推進コンソーシアム 15年の活動の軌跡」発刊にあたって
昨年2020年に活動開始から15年を迎え、その活動内容を「15年の活動の軌跡」としてまとめられた地域力共創推進コンソーシアムさんに取材させていただきました。
取材は8月31日火曜日に山形市市民活動支援センター「ふらっと」にて。当日は、これまでコンソーシアムの活動を支えてきた中心メンバーであるSKソリューションズ代表 黒沼貞志さん、おきたまラジオNPOセンター代表 山口充夫さん、AISOHO株式会社 取締役 菅野美奈子さんの3人に当センターまでお越しいただき、お話を伺いました。
活動の始まりは、平成18年度山形県の「NPO協働企画提案委託事業」への応募から。 「One Coin 地域力 カフェ」「コミュニティビジネス(CB)アイディアコンテスト」「地域力倶楽部」という3つの事業で見事採択されたのがはじまりでした。助成金額は50万円という決して少なくない額でしたが、その予算のなかで3つの事業を運営するのは相当の苦労だったようです。
しかし、本当に大変だったのはここからでした。代表である黒沼さんいわく、黒沼さんのもうひとつの顔であるコンサルタントとして、日頃人に事業の「継続」の大事さを説いていただけに、自主運営となる2年目からの活動はできないとはどうしても言えなかったと、苦笑まじりに話されていました。
そこから気が付けば10年が経ち、その節目として記念フォーラムの開催。ここで活動は一つの区切りを迎えます。ここで少し休もうかと思ったこともあったそうです。けれどもう少し、できる限りのことを続けたいとの思いから、活動の回数を減らすなどして活動を継続していきます。
そして迎えた15年目、今度はコロナ禍が襲います。
この1年は「‘‘コンソ15年の活動の結果(軌跡)‘‘を制作する年」と位置づけ、デジタルブック制作にとりかかることになります。
コンソーシアムの活動の始まりである県の支援事業に応募しようとしたそもそもの思いを、改めて黒沼さんにお聞きしました。「産・学・官・民」(民=ボランティア、NPO活動など)それぞれの領域の間、連携・協働の領域で何かやれたらいいと考えたといいます。また、ビジネス系産業・学校・行政、それぞれの側からの必要性も強く感じたそうです。それには当時コミュニティビジネスといわれたもの(現在でいうソーシャルビジネス)がその間を取り持つ上で有効と考えました。
中間的立場の事業で、いろんな人やものをつなげないか?その考えが、今も常に基本になっているようです。
そんな思いの結晶である「OneCoin地域力カフェ」。『地域力』という言葉でくくることで、ジャンルを限定せず、面白いことを元気に発信しつづけた企画です。
当初山口さんは一般参加者としてこのカフェに参加したそうです。その活動の魅力にひかれてネットラジオで紹介するうちに、話題提供者としても加わるようになり、気が付けば活動の中心的メンバーになっていきます。
一方、初期から中期にかけて重要な役割を担ったラジオモンスターさんは、村山総合支庁委託事業「CB公開起業オークション」がきっかけとなり、オークションで事業発表された菅野さんのつながりから参加されたそうです。そこからもう一つの活動の柱となる”放送メディアを通じたコミュニケーション”「Yamagata地域力ステーション」がスタートし、9年間で200回の番組を放送しました。
”Face to Face のコミュニケーション”「One Coin 地域力 カフェ」の14年間での開催回数は100回。約1,400人の参加者。これは1回あたり14人の参加となるそうです。また、新規参加者の割合は約25%。つまり1回あたり3.5人の新しい広がりがあったということになります。黒沼さんは言います。「活動の半分は次の人をつくること」。14年の継続の間に、次のタネが植えられていったのでしょう。
『地域力』とは何なのでしょう?
「OneCoinカフェで得たものを生かすも殺すも聞いた人それぞれ。それが『地域力』を育むことが出来るかにつながる。」再び山口さんの話です。「このコンソーシアムだけではなく、ここに関わったすべての人が育んでいくべきもの。話題提供者とのかかわり方はその場のものだけではなく、その後のようすも追いかけて、場合によっては現場にも足を運ぶ。それが『地域力』を育むことにつながっていく―。」
「思わない限りできない。着想、発想のもとは好奇心から生まれる」。これは黒沼さんの言葉です。
今回お話を伺って、いかに「継続」することが大事か、教えられた気がします。一方、「継続」することの困難さも相当なものだったでしょう。当時のことを今は思い出話として、時に笑い話として振り返る3人の顔からは、ある種の達成感のようなものも感じられました。

最後に今後の活動についてお伺いしました。
OneCoinカフェの今後の展開として、先を見据えた国際化と多様性で英語を学んでいくのはどうかというのは、その場で菅野さんから出たアイデア。健康でいるための新たなコミュニティの構築といった構想も、熱く語っていただきました。また、これまでのOneCoinカフェ・移動カフェの企画をパッケージ化して、他団体へ提供していったらどうか?そんなアイデアも飛び出しました。
それらは冊子の「第Ⅱ章 発刊に寄せて」の中に記されていた『「地域」の構成要素・要件が大きく変化し、地域の「多様性」が加速する時代が既に到来している』というコメントが念頭にあるからとのことでした。
コロナ禍でなかなか思うように会って話をすることもできず、コロナ禍明けの活動もまだ白紙とのことですが、今後の活動の構想を話し合う3人は、これからの展開にとてもワクワクしているように見えました。
着想と思いつき。
思わない限りできない。思ってもできないかもしれない。その思い付き、着想、とっかかりが「好奇心」。
おもしろいと思ったらすぐやる。好奇心とフットワーク。
それらの思いとともに、まだまだ「地域力共創推進コンソーシアム」の活動は続いていきそうです。
「地域力共創推進コンソーシアム 15年の活動の軌跡」は以下のURLにて公開しています。ぜひ一度ご覧ください。
さまざまな活動の「タネ」が、きっと見つかると思いますよ。

・掲載サイト ⇒ https://sk-solutions.org/about/consortium
・デジタルブック ⇒ https://sk-solutions.org/RPCC15th/index_h5.html#1
正誤表はこちらからダウンロードできます。(pdf)
■お問い合わせ先
地域力共創推進コンソーシアム
代表 黒沼 貞志
電話 090-2522-4548(黒沼)
Eメール: sks@sk-solutions.org