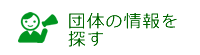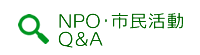「手話まつり」が開催されました!
全国手話通訳問題研究会山形県支部
平成23年1月22日土曜日、山形ビッグウィングにて「手話まつり」が開催されました。
主催したのは、「全国手話通訳問題研究会山形県支部」の他、「一般社団法人山形県聴覚障害者協会」「山形県手話サークル連絡協議会」の3つの団体です。


山形県で初の試みの「手話まつり」。広く市民の方に、聴覚障がいについて理解してもらい、手話に触れてもらうことを目的に開催されました。
「聴覚障がい」はなかなか外から見えにくく、実際に障がいを持っている方はどんなところで不便さを感じるのか、聞こえる人と何が違うのかなど、社会の中でまだまだ理解されていない面があるそうです。
聴覚障がいを持っている方は、「バスのガイダンスは音声だけなので次の停留所がわからない」「子どもの謝恩会に手話通訳が派遣されなかったことで、お世話になった先生にも御礼を述べられず、思い出のスピーチも聞こえず、友達の親との会話も満足にできなかった」「聴こえない人に音楽会の手話通訳はいらないと思ったと言われた」など、暮らしの中で様々な“生きづらさや不便さ”を感じているそうです。
障がいを持っている方のそうした“生きづらさや不便さ”を少しでもなくすため、地域で「聴覚障がい」や「手話」の理解を広めていくことがこの催しの目的です。
当日は、手話サークルの活動内容を紹介するパネル展示や聴覚障がいについての相談コーナー、ろう体験コーナー、ミニ手話教室などが行われていました。また、聴覚障がいを持つ人の苦悩と希望を描いた映画「ゆずり葉」の上映会が行われ、約200名の方が来場されたそうです。



私も「ろう体験」を体験させてもらいました。耳に、耳栓とヘッドホンを装着し、音を遮断した状態で、人の話すことばや伝えたいことを理解する体験です。
体験してみると、言葉を口の動きだけで読み取ることは困難で、身振り手振りをつけてもらいやっと読み取ることができました。
また、聴覚障がいを持っている高校生とその友達が一緒にろう体験をし、「友達の持っている障がいを体験してどんなことに困るのか、困った時どんな気持ちになるのかを知ることができました」と感想を話してくれたそうです。

右の写真は、手話初心者もすぐに参加し学ぶことができる「ミニ手話教室」の様子です。教えているのは、干支の十二支の動物の手話。身振り手振りもつけながら、子どもたちにも分かりやすく教えていました。
「全国手話通訳問題研究会山形県支部」は、聴覚障害者福祉と手話通訳者の社会的地位の向上を目指し活動しています。主な活動として、手話通訳者や手話通訳に関わる方の学習や交流の場の開催や、聴覚障がいがある方が、手話や要約筆記などの手段を使って必要な情報を適切に受発信できるの制度確立のための活動を行っています。現在、山形県支部の会員は77名で、手話を習得していなくても、聴覚障がいや手話に関心がある方ならどなたでも会に参加することができるそうです。

今後の活動について代表の鈴木章子さんにうかがったところ、「今回のような、市民の皆さんに聴覚障がいの理解を広めていくことや手話を普及していく活動により力をいれていき、聴覚障がいを持つ方が不便さや生きづらさを感じない地域にしていきたいと考えています」と話してくださいました。
聴覚障がいを持つ人と共に歩みながら、障がいを持つ方が安心して暮らせる地域を目指し活動している全国手話通訳問題研究会山形県支部。今後も、聴覚障がいを持つ方がどんな助けを必要としているのかを把握して当事者に寄り添い共に歩んでいかれるそうです。