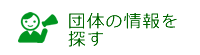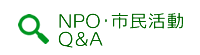山形音楽療法士会は、山形県内の音楽療法の普及と向上、および発展に努めることを目的に活動している団体です。
活動場所は主に病院や老人ホーム、作業所などの各施設で、音楽を用いた治療活動を行っています。その活動のひとつとして、定期的に会員を対象とした研修会を開催しています。今回は仙台から講師をお招きしたため、一般の方にも音楽療法を知ってもらいたい、ということで募集をしたところ、会員の他に16名の参加がありました。

初めに、代表の平間さんから講師の紹介がありました。講師の植木さんは、日本音楽療法学会認定音楽療法士で、現在は東北労災病院緩和ケア内科に勤務しています。今回の研修会では、労災病院で体験したことと、東日本大震災の後に被災地に行き、そこで気づいたことなどをお話いただきました。

研修会では、テーマとなっている「寄り添う」という言葉の意味を、音楽療法の視点から説明していただき、併せて、重病の患者(クライアント)や認知症の方への治療はどうするのか?ということについて、事例を交えながら皆さんで考えていきました。
紹介いただいた事例は、重度認知症の方とその家族に対する音楽療法、脳梗塞の後遺症で機能障害となった方が音楽療法をきっかけに社会に復帰していったことなど3件。どのケースも、患者が抱える問題が異なっていましたが、音楽療法を用いて試行錯誤をしながら、気持ちに「寄り添う」ことで周囲との関係性や患者の状態が良くなっていったことがわかりました。
事例の中では、うまく音楽療法ができず中断してしまったことや、最後を看取るまで音楽療法ができたことも含まれていました。そのような経験から、植木さんは音楽療法をする上で、患者の心の底の望みをきちんと聞く、そのためにどうすればいいか考えながら仕事をしているそうです。


また、実際に音楽療法をしている様子(歌を口ずさむ、ピアノの練習)を録音したCDを流す場面もありました。講師の植木さんに後からお聞きしたところ、治療のときに毎回録っているわけではなく、紹介するときも事前に本人(または家族)の許可を得ている、とのこと。機能障害の方がピアノの練習をしている演奏を聞いたときには、一生懸命な様子が伝わってくるようで、参加した皆さんも機能障害の患者さんとは思えない、と驚いていました。

来年度の活動については、継続的に研修会をして行くとともに、今回のように一般の方に対して、音楽療法を理解してもらう機会を増やしていきたいと話す、平間さん。
音楽療法と聞くと、歌を一緒に歌う、曲を聞かせて安心させるというイメージを持っていましたが、患者の症状の緩和や行動の変化だけでなく、生きる希望を見つけるきっかけにもなることを知りました。これからも、研修会や実際の演奏などを通じて、音楽療法を身近に感じられるような活動を続けていってほしいと思います。
- お問い合わせ先
山形音楽療法士会
Eメール:ffmi3515jp@yahoo.co.jp